夫婦間でさえ違う『金銭感覚』、子どもにどう教育すべき?【専門家が回答】

「お金ってなんで必要なの?」何気ない子どもの質問に、ドキッとしたことがあるママたちに向けて。タッチーこと田内学さんの連載が復活!今回は、子どもの金銭感覚について悩むママにお答えします。
こちらの記事も読まれています
▶︎【子どもの金銭感覚】どう養う?「なんでも簡単に手に入る」とならないための考え方
元GS、社会的金融教育家・田内 学さんが回答!
ママのための「お金の教育」悩み相談室
今月の戸惑うママ(30代 共働き、6歳年長、4歳年少のママ)
中高一貫共学校の家庭科教員であるUさん。田内さんが登壇した教員向けの講演会に感銘を受け、今回の対談を希望してくださいました。
“私もお金の使い方は特に教えていません”
田内 学さん(以下、田内) いま6歳のUさんのお子さんはお金について、どの程度興味があるんですか?
読者・Uさん(以下、U) 半年くらい前にゲームセンターデビューしたのですが、そのせいか、なんでも100円玉で換算するんです。「外でご飯を食べたら、100円玉何枚分なの?」「この間のクレーンゲームは100円玉4枚分だけど、ご飯が○枚分なら、もったいないから行かない」という感じです(笑)。今はほほえましいのですが、中学生とかになると「友だちと遊びに行くから5,000円ちょうだい」などと言われるのかなと…。例えば、中学生になったら友だちとの外食はおこづかいにするとか、親がいくらまでと決めて出すとか、基準を作っていけばいいのでしょうか。
田内 難しいですよね。それに関する正解はないと思っています。でも、お金に限らず、人は挫折して学ぶことはたくさんある、というのが私の考え方。おこづかいの使い方で多少しくじっても、将来的に大きく困るといったことにはならない気がします。自分で学んでほしいので、私はあえて細々したお金の使い方については子どもたちに教えていません。
U え、そうなんですか⁉意外です。
田内 いつも本に書いているような、お金と社会の仕組みを話している程度です。大人でも子どもでも、自ら学ぼうとするのは自分が本当に困った時だと思います。「海外に行った際に話せないと困るでしょ?」と英語を無理やり勉強させられても身が入らないけれど、実際に海外で英語が使えずピンチに陥ったら、本気で取り組むのではないでしょうか。
U 確かにその通りですね。思えば、私自身が中高生時代にお金がなくて我慢することが多かったんです。それに比べていまどきの子は、我慢する機会が少ないように見えてしまって。それで心配になったのかもしれません。というのは、私は関西の中高一貫学校で教員をしているのですが、その生徒たちに日帰りで行く校外学習のアンケートをとったところ、「テーマパークに行きたい!」という回答がちらほらあって。行き帰りの交通費も含めるとかなりお金がかかるのですが「親が出してくれるから」という感覚のようなんです。他にも複数の生徒たちとの雑談で「テーマパークで2万円使った」「必要になったら、その都度親がお金を出してくれる」という声を聞くことがあります。学校の帰り道、友だち同士でカフェに寄るのもしょっちゅう、といった子たちも。各家庭の事情や考えが違うのは重々承知ですし、生徒たちにきちんと予算を提示すればそこに収まるところを提案してくれると思いますが、とはいえ若い子たちのこういう感覚を間近で見ていると、「我が子のお金の価値観は、今後どうなっていくのだろう」と心配になってしまうんです。我が家は平日忙しく外食も多いのですが、そのたびに子どもは喜んでくれます。喜んでくれる一方で、「望めばなんでも簡単に手に入ると子どもに思わせてはいけない」と考えてしまう自分もいます。とはいえ、子どもが求めるものを我慢させすぎて、お友達と足並みが揃わないことがあったらかわいそうだなと思ってしまったり…。私の中でもかなり揺らぎがあります。

夫婦間でさえ違う金銭感覚、それを隠さず伝えて。それがやがてシチズンシップにきっとつながる
田内 多数派に足並みを揃える「同調圧力」という言葉がありますが、実は日本はそれほど高くないらしいんですよ。それよりも、「他人から自分がどう見られるかを気にしてしまう人が多い」という調査結果を先日見かけました。Uさんの生徒さんたちも周りに無理やり足並みを揃えているのではなくて、「行けない、払えないと思われるのがダサい」と思ってお金を使っているのかもしれないですよね。
U そうかもしれないです。そうなると、「人の目を気にせずに、自分で必要と感じたものだけにお金を使って」と教えてあげると効果的なのでしょうか?
田内 先ほどの「必要になったら学ぶ」につながりますが、親が計画的にお金の使い方を教え込むより、やっぱり一回本人が失敗したほうが早いのかもしれない。例えば、中学生ならおこづかいを毎月3,000円ではなくて、一気にまとめて1年分、3万6,000円渡してしまうとか。極端ですが。自分で使い道を考えて、失敗すると何を優先するかという感覚が芽生えるかもしれません。
U うちの子なら、100円玉20枚、とかですかね。確かに最近は「クレーンゲームで使うのと同じだけの100円玉で、お菓子を買ってもらったほうがいい」とも言っています。そのくらいの感覚なら身についているのかも。今思い出しましたが、子どもに「なんでいつもママが決めるの?」と聞かれて困ったことがあったんです。例えばクレーンゲームは1日3回までにしているのですが、「なんで3回って決めるの?」と。どう答えたら良かったんでしょうか。
田内 ママだって、お給料が決められているわけじゃないですか。その相似形として、説明してはどうでしょうか?
U 確かに!そういえば、自分にも毎月決まった額のお給料があって、その中で使い道を決めて…というような話はしたことがなかったです。私自身の買物に付き合ってもらうこともあるので、子どもにとっては「ママは自由にお金を使っている」と思っているのかもしれません。
田内 Uさんのお話を聞いていて、金銭感覚の身につけ方をどうするかというより、大人と子どものお金に対するギャップを理解したほうが、不安が解消するのではないかと思いました。そして子どもにあれこれ教える前に、まずは自分のお金の使い方を考えて、直せるところは直してみるといいかもしれませんね。その上で、自分自身は限られた金額でやりくりしている実感があるなら、「ママはこうやっているんだよ」と教えてあげると、子どもにとっては納得しやすいのではないかと思います。ところで、パパのお金の使い方はいかがでしょうか。
U 実は、夫がおもちゃをバンバン買ってくるタイプなんです(笑)。それなのに夫からは、「それより外食費がもったいないから、回数を減らしたら?」と言われます。特に平日は子ども2人をワンオペ対応なので忙しいですし、外食は必要経費だと思っていたのですが…。
田内 子どもはなんでも買ってくれるパパのことを慕うのに、「買い与えないほうが子どものため」だと思っているママには不満を募らせる。このような「夫婦間ギャップ」があるご家庭も少なくないと思います。夫婦でお金の話をすると衝突するから、あえて避けているという話も聞きますが、Uさんのところは?
U 特にこれまで必要性を感じていなかったんです。でも子どもがゲームセンターやお金に興味を持つようになったのがここ半年くらいなので、もし話すとしたら今ですよね。
“家庭も小さな社会。おもちゃを買う理由、外食する理由を話してみては”
田内 それこそが、Uさんの悩みを解消するポイントなのかもしれない。家庭は小さな社会です。たくさん人がいればそれだけお金の使い方も異なりますが、身近にいる父と母でもこれだけ金銭感覚が違う。それをお子さんが学ぶ、いいきっかけになればいいですね。同様に、親子ほど年が離れたUさんと生徒さんたちの金銭感覚が違うのも当然ですしね。
U 本当にそうですね。以前、田内さんが教員向けに行った講演会で「『社会に役立つことをすることでお金がもらえる』という基本を子どもたちに教えたい」と仰っていて、とても感銘を受けたんです。我が子にもいつか、社会の仕組みやシチズンシップについて教えていきたいと考えていましたが、家庭も社会ですよね。
田内 家事を手伝うことで家族を助けるというのも、「社会の役に立つ」ことの一つです。税金の話も本当は学校でもっと横断的に教えたほうがいい、と思っているんです。Uさんは家庭科の教員ということで、家計管理についても指導されていると思いますが、社会の授業と連携できればもっと理解が深まるはずで。小学校では、漁師が釣ってきた魚を市場で売る人がいて、それをお店で売る人がいるから私たちが魚を食べられる…という社会の流れを教えてくれます。それが中高生以上になると、社会科では市場経済の話をして、家庭科では家計のやりくりの話といったように、教科が分かれてしまいます。リンクしていないから、自分が社会の一員であることの意識が希薄になってしまう子が多いような気がしているんです。
U とても腑に落ちました。私も無責任なことは言えないのですが…みんなのために誰かが何かをすべきという場面で「自分が損をすることはやりたくない」という生徒の様子を見ることもあり、コミュニティのつながりや貢献への意識の違いが気になることがあります。我が子にも生徒にも、自分が社会、集団の一員であること、みんなのために何をすべきかという視点を持てるよう、育てていきたいと改めて感じました。教員としての学びも多いお話ができて、とても満足しています。ありがとうございました。

田内 学さん
1978年、兵庫県生まれ。2001年、東京大学工学部卒業。2003年、同大学院情報理工学系研究科修士課程修了後、ゴールドマン・サックス証券入社。日本国債、円金利デリバティブ、長期為替などのトレーダーに。2019年に退職後は、子育てのかたわら、金融教育家として講演や執筆活動を行っている。@tauchimnbで経済やお金の情報を発信中。
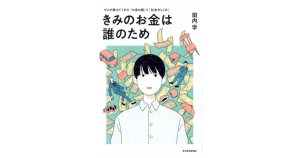 『きみのお金は誰のため
『きみのお金は誰のため
ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』
田内 学著 ¥1,650/東洋経済新報社
中2の優斗はひょんなことで知り合った投資銀行勤務の七海と謎めいた屋敷へ。そこにはボスと呼ばれる大富豪が住んでおり「お金の『3つの謎』を解けた人に屋敷を渡す」と告げられる。大人も子どもも一緒に読みたいお金の教養小説。
あわせて読みたい
▶︎VERYママの【子どものお小遣い事情】専門家がすすめる「正しいお金との付き合い方」とは?
▶︎新入学・進学時は考えどき!【子どもの“報酬制”おこづかい】メリット・デメリットって?
▶︎東原亜希さん「子どもにはお金の増やし方より“稼ぐことの楽しさ”を伝えたい」
イラスト/犬ん子 撮影/吉澤健太 取材・文/樋口可奈子 編集/中台麻理恵
*VERY2025年3月号「ママのための「お金の教育」悩み相談室」より。
*掲載中の情報は誌面掲載時のものです。
