子どもの「これ買って」は仕方ない?“欲しがらせる消費”の時代に考えたいこと

「お金ってなんで必要なの?」何気ない子どもの質問に、ドキッとしたことがあるママたちに向けて。社会的金融教育家・田内学さんの連載が復活!今回は、3歳の長女がなんでも「これ買って」と言うようになって悩むママの疑問にお答えします。
こちらの記事も読まれています
▶︎【おこづかいって意味あるの?】お金の価値観を学んでほしい時に意識すること
元GS、社会的金融教育家・田内 学さんが回答!
ママのための「お金の教育」
悩み相談室
今月の戸惑うママ
Sさん(30代・共働き、0歳、3歳の女の子ママ)
今年の春に出産、現在育休中。共働きの夫も育休を2カ月とったものの夏以降はワンオペで、初の2人育児に奔走中。
モノがあふれる今、
「欲しがらせる消費」が増えている
田内学さん(以下、田内) お子さんは主にどんなものを欲しがるのでしょうか?
読者 Sさん(以下、S) お湯に入れるとキャラクターの人形が出てくるバスボムにハマっていて、毎日のように買って買ってと言われます。それが1個500円もするんです!塗り絵も、ちょっと塗っただけで「新しいの買って?」となりますし、フルーツが好きなのでスーパーに行くと何種類もカゴに入れてきたり。「こんなにたくさん買えないよ」「働かないとお金はもらえないんだよ」と伝えているけれど、どこまで伝わっているのか。もちろんまだ3歳なのでしょうがないですが、このまま大きくなっても理解できないのはよくないよなと…。
田内 「買えないよ」と言うと、お子さんはどんな反応をしますか?
S 特に癇癪を起こすようなことはないですね。聞き分けはいいほうかも。フルーツも3種類くらい入れてくるので、せめて2つにしよう、と説得すると納得してくれることも多いです。
田内 うちの子も、同じ年頃にバスボムにハマっていました。人形がたくさん溜まっているのを見て、「一体いくら使ったんだろう?」と気になったこともありましたが、子どもと一緒に買物に行くのは主に妻だったので、きっといろんなやりとりがあった上で買ったのだろうなと想像しました。夫さんは、お子さんがなんでも欲しがることに対して、何か思うところはありそうですか?
S 子ども関連用品は私の財布から出していることもあって、特に何も言わないです。我が家はかなりきっちり分担していて、家賃と保育料は夫持ち。光熱費は私持ちなのですが、育休中の今は夫が払っています。食費や子ども関連用品、生活用品は私が出していて、家電などの大物は共有している資金から購入します。交際費は都度精算、家族で楽しく外食したときは割り勘です。
田内 なるほど、カテゴリによって支払いは別々なんですね。貯蓄に関してはいかがですか?
S お互いに貯金ができないタイプで、互いの貯蓄も把握していなくて。賃貸派で、家を買うつもりがないということも大きいです。教育資金として、子どもが中学校を卒業するまでにはお互い600万円ずつ貯めていればOKで、貯め方は自由という取り決めをしています。私も自由に使えるお金がないとストレスが溜まるので、そのためにも会社員を続けているという感じです。財布を分けることで、お互い詮索されたくないところに踏み込まなくていいのもラクです。光熱費が私持ちだったときは、夫がつけっぱなしにしていた電気やエアコンを黙って消していたんです。5回に1回くらいは「消してね」と言ってしまっていましたが、もしかしたら夫は「すぐ戻るから」と思ってつけっぱなしにしているのかもしれない。夫には夫の理由があるだろうから、あれこれ聞くのもしつこいかなと。今は光熱費が夫持ちなので、前より言わないで済んでいるかもしれないですね(笑)。

500円のバスボムを毎日「買って?」
田内 お互いの担当領域に口を出さないというのは、夫婦の揉め事を防ぐやり方の一つとしていいと思います。子ども用品の担当がSさんだから、夫さんは「バスボムを買いすぎ」とは言いづらいでしょうし。この連載で「お手伝いしてお金を渡すってどうなの?」という話がよく出るのですが、この方法だと「家族の助け合い」のはずなのにお金を要求することになりかねない、という問題があるんです。しかし例えば子どもに〈光熱費担当大臣〉になってもらい、予算から抑えられた一部を払う方式であれば、子どもも電気の無駄遣いを気にするようになるし、家族も実際に助かりますね。ところで、ここまで話を聞いていると、お金に対してモヤモヤと悩むポイントが実はない気がするのですが。
S 確かに夫はうるさくないのですが、実母が何かと「もったいない」と言ってくるのが引っかかっています。下の子が生まれてすぐの1カ月間、実母が泊まり込みで手伝いに来てくれたのですが、私が上の子になんでも買ってあげるのを見て、「モノを与えたくなる気持ちは分かるけれど、本当は一緒に遊んであげるだけでいいのよ」と言われてしまって。我が家では手洗いは衛生面を考えて使い捨てペーパータオルを使っているのですが、「紙がもったいない」「環境に優しくない」と言われました。お掃除ロボットや食洗機を使うことで、子どもたちが家事を覚えらなくなることも気にしているようです。そう言われ続けると、安くもないフルーツを当たり前に食べられると思わせていること自体も、子どもの教育にとってはよくないのかと思ってしまって…。
田内 お母さんが子育てしていた時代と家事や育児のやり方が変わるのは自然なことで、特に悪いことではないはず。紀元前800年くらいから、「最近の若い人はこれだから」「人間はもうダメだ」と発言した人がいる、という記録が残っているんです。そんなに昔から繰り返されてきた話なのに、今も別に大変なことにはなっていないですからね。世代が変わることで生活様式や考え方が変わるのは当たり前のこと。子だくさんが当たり前だった時代は、皆が皆こんなに教育熱心ではなかったでしょうし。
S 実は今、お惣菜の宅配を頼もうかも迷っているんです。上の子を保育園に送って下の子に授乳して寝かしつけして、それだけで一日があっという間で、もうお迎えの時間という感じで、料理する余裕がなくて。ただ、それについて母がどう思うか気になってしまう自分がいました。母は専業主婦で、家事にも手を抜かず、私と弟に手をかけて育ててくれたんです。ただ、夫も子どもも料理が手づくりかどうかのこだわりはないんです。むしろ買ってきたお惣菜のほうが喜んで食べるくらい。
消費スタイルが昔と今では変化している
田内 希少な資源はお金よりもむしろ時間です。自分の時間の使い方を選べるのは自分だけ。お惣菜を買うことで時間がつくれて、それに幸せを感じるのならそれでいい。便利な家電やサービスで家事時間が減った今、育児に費やす時間が増えたというデータもあります。習い事の送り迎えをしたり本の読み聞かせをしたりと、ゆとりを持った生活が送れているのなら、その分の時間にお金を払ったと考えればいいのではないでしょうか。お母さんの「もったいない」の中にはお金を使いすぎることも含まれているかもしれませんが、子どもにとっては親が買った果物も親戚からもらった果物も、なんの違いもありません。農家の子はフルーツ食べ放題かもしれない。でもそれが「もったいない」と言われないのは、金銭のやりとりが発生していないからですよね。支払うSさんが納得できているのであれば、お子さんの教育上良くないと考える必要はない気がします。
S それを聞いて、ちょっと安心しました。先日、近所のシェア畑を眺めながら、「こんなふうに野菜ってできるんだね」と上の子にしたら、興味を示していたんです。買ってきたフルーツがどこでどうやってつくられているかを話しても面白いかも。重曹とクエン酸、食紅でバスボムを手づくりしたという話を人から聞いたこともあるので、いつか真似してやってみたいとも思っています。母の小言はさておき、なんでもすぐ買って解決してしまうことに罪悪感がなくはないので。
田内 お子さんの「買って買って」と、ご自分のモヤモヤの落としどころがうまく見つかるといいですね。今の時代、お金がもったいないと思う感覚とは別に、消費すること自体に疑問を感じる人は少なくないと思います。戦後はモノが足りないから、みんなが欲しがる家電をつくればそれが売れて、家電をつくるためには鉄が必要で…と、誰かが欲しいものをつくって売ってお金をつくり、それでまた欲しいものを買うという形で経済が循環していました。でもある程度日本が成熟したことで、みんなの欲しいものがお金になってしまいました。使えればなんでもいい、安いものでいいし、欲しくないから買わないとなると、企業は「いかに欲しがらせるか」という視点でモノをつくるようになります。その結果、大人の財布の紐が緩くなるタイミングは「子どものための消費」というパターンになります。バスボムもゲームもガチャガチャも、モノがなかった昔は存在していませんでした。モノがあふれる現代だからこそ、子どものための消費をうながす広告や宣伝が増えています。しつこいようですが、上の世代とは消費のスタイルも異なるんです。だから、ついバスボムを買ってしまうのもしょうがないと思ってもいいと思いますよ。
S ありがとうございます。産後で母と一緒に過ごす機会が多かったから、これまでよりも母の価値観に影響を受けやすくなっていたような気がしてきました。これからも私なりに、気楽にがんばります!

田内学さん
1978年生まれ。2001年、東京大学工学部卒業。2003年、同大学院情報理工学系研究科修士課程修了後、ゴールドマン・サックス証券入社。日本国債、円金利デリバティブ、長期為替などのトレーダーに。2019年に退職後は、子育てのかたわら、金融教育家として講演や執筆活動を行っている。@tauchimnbで経済やお金の情報を発信中。
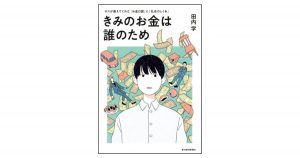
『きみのお金は誰のため
ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』
田内 学著 ¥1,650/東洋経済新報社
中2の優斗はひょんなことで知り合った投資銀行勤務の七海と謎めいた屋敷へ。そこにはボスと呼ばれる大富豪が住んでおり「お金の『3つの謎』を解けた人に屋敷を渡す」と告げられる。大人も子どもも一緒に読みたいお金の教養小説。
あわせて読みたい
▶︎子どもが『ゲーム課金』沼にハマったら?自分のお金で“失敗する機会”も大事
▶︎ねだる子どもには【お金という道具を使って取捨選択すること】を学ばせるのがベスト!な件
▶︎夫婦間でさえ違う『金銭感覚』、子どもにどう教育すべき?【専門家が回答】
撮影/吉澤健太 イラスト/犬ん子 取材・文/樋口可奈子 編集/中台麻理恵
*VERY2025年9月号「ママのためのお金の教育悩み相談室」より。
*掲載中の情報は誌面掲載時のものです。
